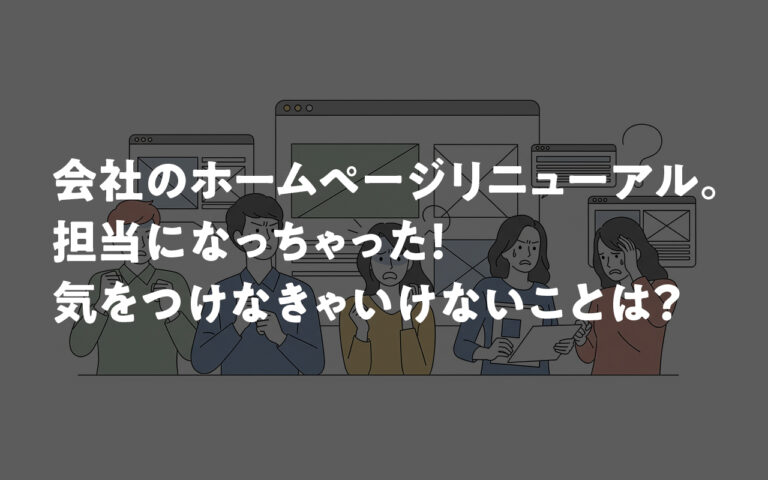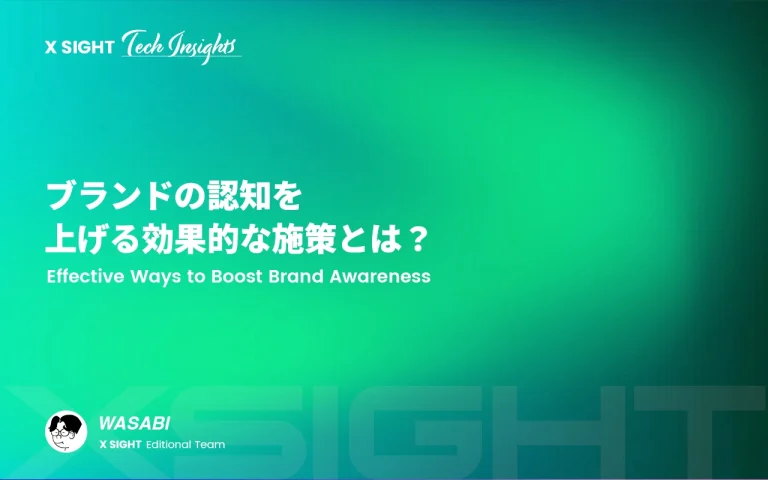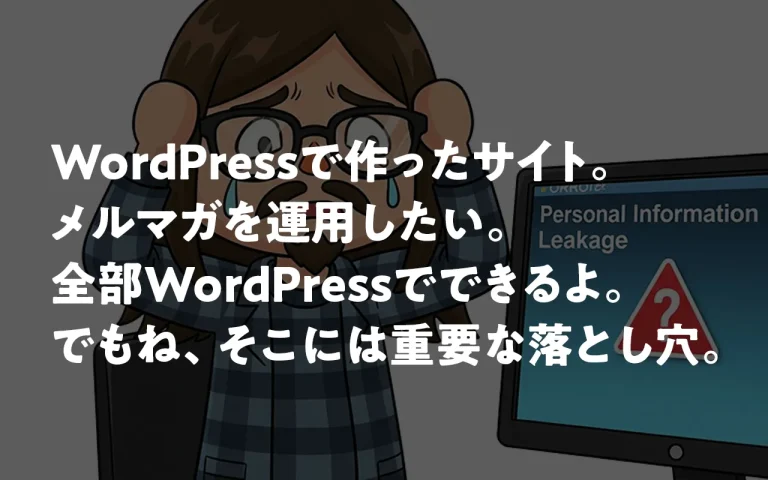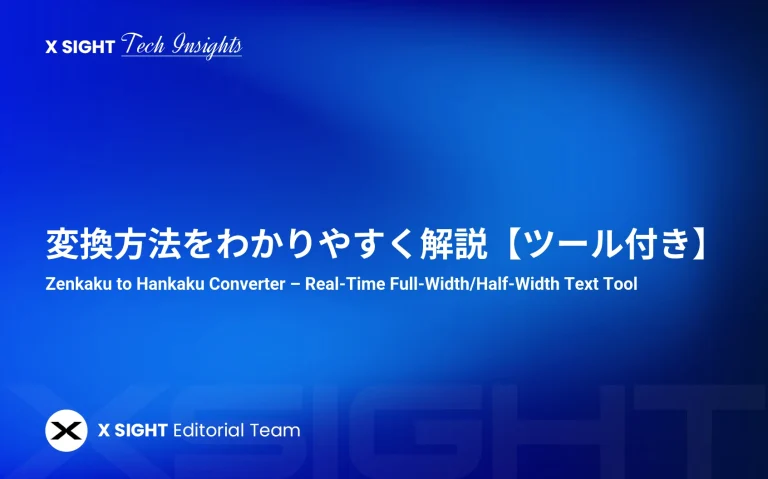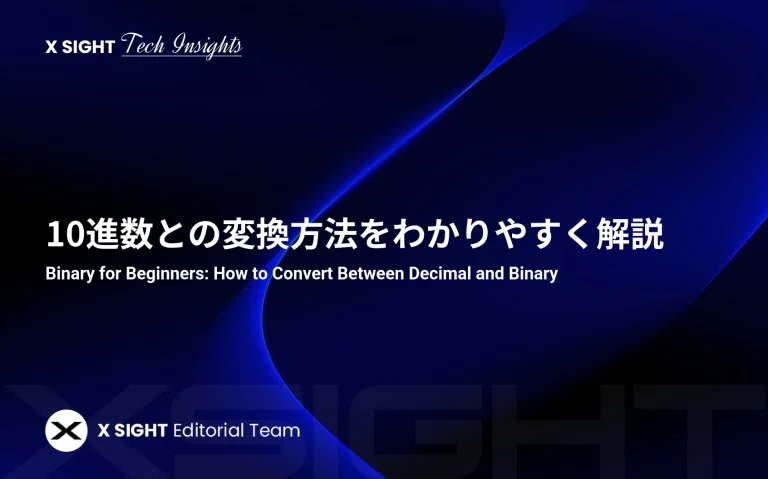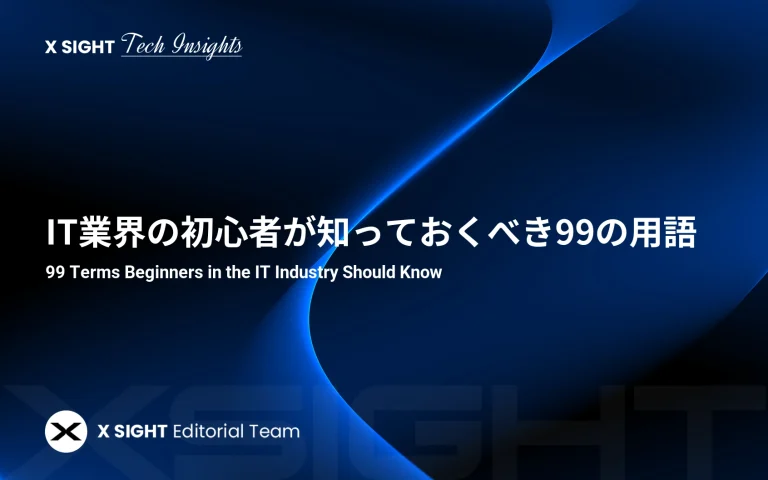【初心者向け】日本の国技 相撲【第2回】ルール編|勝敗の仕組みから番付・決まり手まで

前回の記事では、「歴史編」と題し大相撲の成り立ちを説明させていただきました!
そのうえで、今回は「基本ルール編」です。
詳しく見ていきましょう!
まずは勝ち負けに関して。
相撲は、直径4.55メートルの円形の土俵の上で、2人の力士が「はっけよい、のこった!」の掛け声とともに組み合い、勝敗を競う格闘技です。
勝敗の決め手は、以下のどちらかです。
- 土俵から出る(「土俵を割る」と言います): 相手の体の一部が土俵の外に出た場合。
- 土俵に体がつく: 足の裏以外の体の一部が土俵についた場合。
非常にシンプルですが、このルールの中で力士たちは様々な技を繰り出し、観客を魅了します。
勝負がつくのは2パターンしか無いの?
先ほど説明したのは「土俵から出る」と「土俵に体がつく(足の裏以外)」の2パターン。
それ以外ないのかな?と疑問に思うかたもいるでしょう。
答えは「Yes」です。
その他の場合を見ていきましょう。
- 禁じ手を使う:大相撲の勝負規定では以下の行為が禁止されています。これをやると自動的に負けっす。
・握り拳で殴る。
・頭髪(まげ)を掴む。
・目またはみぞおちなどの急所を突く。
・前立みつ(前ぶくろ)をつかみ、また横から指を入れて引く。
・喉を掴む。
・胸、腹を蹴る。
・指を折り返す。 - 不浄負け:「ふじょうまけ」と言います。要はまわし(関取のまわしは「締め込み」と言う。)が脱げちゃって、大事なものがあらわになっちゃうようなことです。恥ずかしっ。
- 体が無い:「たいがない」と言います。倒れてなくても力士が完全に相撲を取る姿勢を失い、こらえる余裕がないと判断された場合、負けになることがあります。よく「タイが残ってる!」とか「ああ〜、もうこれはタイが残ってないからね〜」などと使います。
取り組みの流れ。
相撲の取組は、ただ力士がぶつかり合うだけではありません。
取組前にはいくつかの儀式があり、これらを理解することで、相撲の奥深さを感じることができます。
- 仕切り: 力士が土俵の中央に立ち、お互いを見つめ合う時間です。精神を集中させ、相手の出方を読み合う重要な時間であり、数回繰り返されます。
- 塵手水(ちりちょうず): 仕切りの間に力士が行う動作で、手を清める意味があります。両手を広げて柏手を打ち、また広げて掌を返す一連の動作です。
- 四股(しこ): 足を高く上げ、力強く土俵を踏みつける動作です。邪気を払い、大地に感謝する意味が込められています。
- 蹲踞(そんきょ): 腰を落として膝を開き、拳を握って前につき出す姿勢です。相手に対する敬意を表します。
- 立ち合い: 行司の「はっけよい」の声とともに、両力士がぶつかり合う瞬間です。ここから取組が始まります。
少し補足すると、1度は力士が水を口に含んだり、塩を撒いたりしているのをご覧になったことがあるのではないでしょうか?
取り組み前にこれらをすることができるのは、いわゆる「関取」以上となります。
関取の地位に至っていない力士の取り組みでは、これらは存在しません。というかお水や塩が土俵の周りに存在しません。
そう、大相撲の世界は完全な実力社会の厳しい世界。
相撲の世界では「番付(ばんづけ)」と言います。力士たちはこの番付が全てなのです。

塵手水(ちりちょうず)の動作。
画像出典:日刊スポーツ

琴栄峰(ことえいほう)の美しすぎる四股。
画像出典:きらりの旅日記

力水(ちからみず)を受ける力士。※この所作は関取以上
画像出典:四国新聞社

清めの塩。※この所作は関取以上
画像出典:Number Web
決まり手を知るとよい面白い!
相撲には82種類もの「決まり手」と呼ばれる勝ち方があります。
すべてを覚える必要はありませんが、代表的なものをいくつか知っていると、より相撲を楽しめます。
- 寄り切り: 相手を土俵際まで追い詰め、そのまま押し出す最も一般的な決まり手。
- 押し出し: 相手を突き押して土俵の外に出す決まり手。
- 投げ: 相手のまわしをつかんで、土俵に投げ倒す決まり手(例:上手投げ、下手投げ)。
- 突き落とし: 相手が前に出てきたところを、引きながら横に倒す決まり手。
テレビ中継では、勝敗が決まった後に「決まり手は〇〇!」とアナウンスされます。
どんな技で勝ったのかに注目してみましょう。

決まり手の館内表示。
画像出典:日刊スポーツ
番付と力士について:相撲界の階級と知られざる待遇の世界
相撲には、力士の強さを示す「番付」という厳格な階級制度が存在します。
この番付によって、力士の待遇や給料が大きく異なり、その差はまさに「雲泥の差」と言えるでしょう。
番付は大きく分けて「関取(関取)※幕内力士と十両力士」と「幕下以下(まくしたいか)」に分かれます。
この2つが、待遇面で最も大きな線引きとなります。
1. 幕内と十両(関取)
十両以上の力士を「関取(せきとり)」と呼び、ここからがプロの力士として認められます。
月給が支給され、付き人がついたり、個室を与えられたりと、大幅に待遇が向上します。
– 関取の階級
横綱(よこづな)
相撲界の最高位であり、別格中の別格。強さだけでなく、品格も求められる、まさに相撲界の顔です。
- 月給: 約300万円。
- 待遇: 専用の運転手付きの自家用車で両国国技館に乗り入れ可能。付け人も15人以上つくことがあります。一度横綱になると、不振でも降格することはありませんが、成績不振が続けば引退が求められます。(引退勧告という。)
▼現在の横綱(2025/07場所)
| 番付 | しこ名 | 所属部屋 | 年齢 | 出身地 |
| 東 横綱 | 豊昇龍(ほうしょうりゅう) | 立浪 | 26歳 | モンゴル・ウランバートル |
| 西 横綱 | 大の里(おおのさと) | 二所ノ関 | 25歳 | 石川県 |
大関(おおぜき)
横綱に次ぐ実力者で、次期横綱の候補とも言える存在です。
- 月給: 約250万円。
▼現在の大関(2025/07場所)
| 番付 | しこ名 | 所属部屋 | 年齢 | 出身地 |
| 東 大関 | 琴櫻(ことざくら) | 佐渡ヶ嶽 | 27歳 | 千葉県 |
関脇・小結(上記の大関と合わせてこれらを「三役(さんやく)」という。)
大関を目指す力士たちが集まる重要な階級です。
- 月給: 月給はどちらも約180万円です。
▼現在の関脇・小結
| 番付 | しこ名 | 所属部屋 | 年齢 | 出身地 |
| 東 関脇 | 大栄翔(だいえいしょう) | 追手風 | 31歳 | 埼玉県 |
| 西 関脇 | 霧島(きりしま) | 音羽山 | 29歳 | モンゴル・ドルノドゥ |
| 西 関脇 | 若隆景(わかたかかげ) | 荒汐 | 30歳 | 福島県 |
| 東 小結 | 欧勝馬(おうしょうま) | 鳴戸 | 28歳 | モンゴル・トブ |
| 西 小結 | 高安(たかやす) | 田子ノ浦 | 35歳 | 茨城県 |
前頭(まえがしら)
いわゆる「平幕(ひらまく)」と呼ばれる階級です。枚数によって上位と下位に分かれます。
最上位の「筆頭(ひっとう)」から最下位の「幕尻(まくじり)」まで。
※幕尻は15枚目と時もあれば、17枚目までいることもある。時によって人数は変動する。
- 月給: 約140万円。
- 特徴: 前頭の中でも、横綱や大関と対戦する上位の力士は注目度が高く、人気力士に勝てば「金星(きんぼし)」を獲得できます。金星一つにつき給金が上がる仕組みもあります。
十両(じゅうりょう)
ここからが「関取」となり、月給が支給される境目です。
- 月給: 約110万円。
- 待遇: 白い締め込み(まわし)を締めることができるようになります。初めて個室を与えられたり、付き人がつくなど、待遇が大きく変わります。
2. 幕下以下(力士養成員)
幕下以下の力士は「力士養成員」と呼ばれ、原則として月給は支給されません。
衣食住は部屋で面倒を見てもらえますが、厳しい共同生活を送ります。
幕下(まくした)
関取のすぐ下の階級で、十両昇進を目指す力士がしのぎを削ります。
- 在籍人数: 東西それぞれ60枚、計120名が在籍します。
- 給料: 月給はなく、本場所ごとに「場所手当」が支給されます(年6回)。場所手当は約16万5千円(月換算で約7.5万円)。
三段目(さんだんめ)
幕下のさらに下の階級です
- 在籍人数: 東西それぞれ100枚、計200名が在籍します。
- 給料: 月給はなく、本場所ごとに「場所手当」が支給されます。場所手当は約11万円。
序二段(じょにだん)
- 在籍人数: 約200~250名程度が在籍します(番付によって変動します)。
- 給料: 月給はなく、本場所ごとに「場所手当」が支給されます。場所手当は約8万8千円。
序ノ口(じょのくち)
最も下の階級です。新弟子がまず最初に所属する番付となります。
- 在籍人数: 約40~70名程度が在籍します(新弟子の数によって変動します)。
- 給料: 月給はなく、本場所ごとに「場所手当」が支給されます。場所手当は約7万7千円。
補足
これらの人数は、各場所の番付によって多少変動します。特に序二段や序ノ口は、新弟子の入門や引退によって大きく数が変わることがあります。
また、場所手当の金額を記載してありますが、本場所は年6回。
ということは2ヶ月に1回、上記の金額が支給されるということです。
幕下以下と十両以上(関取)では、天と地の差があるということがわかります。
関取以上が稽古の時に締めることを許される白いまわし。

画像出典:NHK
幕下以下の力士が稽古や本場所で締める黒まわし。

画像出典:スポニチ
前相撲(まえずもう)とは?
力士と言われる人たちの中には、これまで説明してきた「番付」に載っていない力士も存在します。
番付に載る前の新弟子が最初に参加するのが「前相撲」です。
前相撲の力士はまだ番付に載っておらず、給料も場所手当も支給されません。
相撲部屋で共同生活をしながら稽古に励み、本場所で前相撲を取り、成績によって初めて序ノ口の番付に名前が載ることができます。
まさにゼロからのスタートであり、ここから関取を目指す厳しい道のりが始まります。
まとめ
このように、相撲界は番付によって収入と待遇に大きな差がある「格差社会」と言えます。
しかし、この厳しい競争があるからこそ、力士たちは日々精進し、土俵の上で熱い戦いを繰り広げるのです。
相撲は、単なるスポーツではなく、日本の文化や歴史が凝縮されたものです。(そう、「スポーツ」では決してない。)
これらの基本を知ることで、あなたもきっと相撲の魅力に引き込まれるでしょう。
ぜひ、次の機会に相撲観戦を楽しんでみてください。