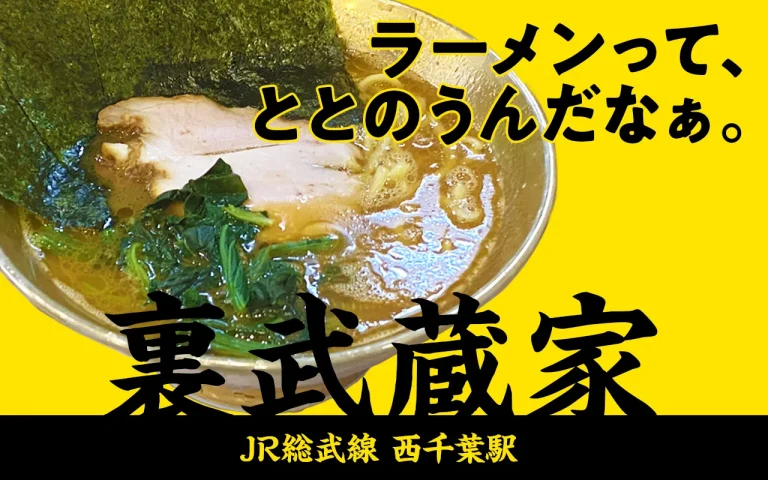日中文化交流史を彩る重要人物【第4回】:鑑真と日本仏教の新たな夜明け

画像出典:唐招提寺公式サイト
はじめに
1300年前、二人の日本僧が胸に抱いた問い――
「なぜ、日本には正式な戒律がないのか?」
その素朴かつ切実なる問いが、やがて一人の唐僧・鑑真との出会いへとつながり、六度にわたる命懸けの航海を生むことになります。
本稿では、鑑真の壮絶な渡航の記録と、奈良の地で築かれた戒律の根本道場「唐招提寺」の誕生、そして彼が日本にもたらした文化の光について、物語として記す。
ひとりの僧の信念が、いかに時を超えて今も私たちに語りかけてくるのか――
その静かな足跡を、共に辿ってみませんか。
1. 「本当の僧」を求めて
――若き僧侶たちが海を越えた理由
奈良時代、733年。
二人の若き日本僧――栄叡(えいえい)と普照(ふしょう)は、はるか唐の地へと旅立ちました。
彼らの旅の原動力は、たった一つの問い。
――「仏教はある。でも、“本当の僧”がこの国にいるのだろうか?」
当時の日本では、「出家します」と言えば誰でも僧侶を名乗れた時代。戒律制度は未整備で、僧籍は時に俗世の逃げ道ともなっていました。
仏教を信じる人はいても、正しく戒を受けた“僧”はいない――そんな危機感が、彼らを突き動かしました。
ふたりは唐で5年を過ごし、数多くの高僧を訪ね歩きましたが、真に納得できる答えをくれる人物には、なかなか巡り会えません。
――そして、運命の出会いが訪れます。
揚州の大明寺にて出会ったのが、名僧・鑑真(がんじん)――当時54歳。
戒律と仏法に通じ、多くの弟子を導く存在。その人物こそ、日本仏教の未来を担う鍵となるのでした。
2.信念の航海
――六度の挑戦が、日本を変えた
鑑真は「日本仏教の父」と称されますが、その来日は決して容易ではありませんでした。
彼は日本の僧侶たちの願いを胸に、六度にわたり渡海を試みましたが、いずれも困難に阻まれます。
初めは讒言で船を没収され出発できず、次には嵐に遭い無人島に漂着、奇跡的に生還しました。
その後も官僚の妨害や自然災害に苦しみ、ついには視力を失い同志も亡くなります。
60歳を過ぎての再挑戦も嵐により失敗し、弟子も帰らぬ人となりました。
しかし、諦めることなく最後の航海に挑み、密かに遣唐使船に同乗して40日の苦難を乗り越え、ついに日本の薩摩の地に到着しました。
この瞬間、鑑真は日本の土を踏んだのです。
3. 唐招提寺と文化の光
――戒律とともに渡った、東アジアの風
754年、鑑真は平城京に迎えられ、東大寺にて聖武上皇と孝謙天皇に正式な授戒を行います。
これが日本仏教史上、初の「正規の戒壇」による授戒となりました。
日本の僧が、仏の道を正しく歩むための大きな第一歩でした。
当時の日本は、仏教を国の柱に据えようとしていました。
国家鎮護の思想のもと、大仏造立や仏教制度の整備が進みつつあり、僧侶の資格を厳格に保つ「律(戒律)」が欠かせない時代でした。
その後、鑑真は新田部親王の旧邸跡を賜り、唐招提寺を建立。
戒壇院を有するこの寺は、日本における律宗の中心となり、仏教制度の完成を象徴する場となります。
鑑真がもたらしたのは戒律だけではありません。
建築、彫刻、医学、書法など、唐の高度な知が日本に新たな息吹をもたらしました。
特に唐招提寺の仏像たちは、唐の美と日本の祈りが交差する存在。
なかでも鑑真和上坐像は、日本最古の肖像彫刻として知られ、今もなお静かに人々を見守り続けています
4.静かなる終焉
――「この戒を、永遠に」
763年(天平宝字七年)五月六日、鑑真は奈良の地で76歳の生涯を静かに終えました。
弟子たちはその最期を予見し、生前の姿を写した干漆像(国宝)を制作。
現在も唐招提寺の御影堂に安置され、毎年六月に特別公開されます。
穏やかな面差しに、今も多くの人が手を合わせ、静かな祈りを捧げます。
俳聖・松尾芭蕉は、こう詠んでその志を讃えました。
世の人の見付ぬ花や軒の栗
人知れず咲く花のように、鑑真の志は、時を超えて静かに輝き続けています。
鑑真の墓は、唐招提寺御影堂の東、小さな林の中にひっそりと佇んでいます。
その場所に、今も香煙が絶えることはありません。
5. 日中を結ぶ志
――信念と誠心がつなぐ、日中を結ぶ架け橋
入滅に際し、鑑真はこう遺しました。
「私はこの国に戒律を伝えるために来た。たとえ私がいなくなっても、この教えを決して絶やしてはならない」
この言葉は弟子たちの胸に深く刻まれ、唐招提寺は律宗の総本山として、日本仏教の柱のひとつに成長していきました。
そしてその精神は、戒律にとどまらず、建築・医学・美術・教育を通して日本文化の根底に息づいています。
現代中国の詩人・郭沫若もその功績を称え、こう詠みました。
鑑真盲目渡東海,
一片精誠昭太清,
唐風洋溢奈良城
視力を失っても、海を越えた鑑真の精誠(まごころ)は、奈良の空に唐の風を吹かせ、今も日中両国の心を結び続けています。
6.おわりに――鑑真の精神は、今も生きている
六度にわたる渡海、幾多の失敗と別れ――
それでも志を曲げなかった鑑真の姿は、現代を生きる私たちにも、静かに語りかけてきます。
彼が残したものは、ただの戒律ではありませんでした。
それは文化を越え、時代を越えて人の心を照らす「道」そのものであり、日中をつなぐ永遠の架け橋なのです。
次回予告
記事に関するご注意
※本シリーズは歴史的記録に基づきながら、一部に物語的解釈・現代的視点を交えて構成されています。解釈には諸説あり、学術的定説と異なる場合があることをご了承ください。